第一章 遠い国からの訪問者
ケイト・マクラーレンは、ネバダ州ラスベガスの郊外に住む二十四歳の女性だった。砂漠に囲まれた故郷で育った彼女は、いつも東洋の神秘的な国に憧れていた。祖母が遺してくれた僅かな遺産を手に、彼女は決意した。日本に行こう、と。
パスポートを手にしたとき、彼女の手は震えた。生まれて初めての海外旅行。少しばかりの円を財布に入れ、彼女は成田空港に降り立った。
空港から都心へ向かう電車の中で、ケイトは窓に顔を押し付けるようにして外を見つめた。整然と並ぶ住宅、清潔な街並み、規律正しく動く人々。すべてが新鮮だった。
初日の夜、彼女は勇気を出して回転寿司店に入った。そして、目を疑った。お寿司が本当に回っている。ベルトコンベアの上を、色とりどりの皿が流れていく。ケイトは子供のように歓声を上げ、スマートフォンで動画を撮り始めた。隣の席の家族連れが微笑んでいる。
「美味しいですか?」
片言の日本語で尋ねると、若い母親が優しく答えてくれた。
「デリシャス! とても!」
人々は親切だった。言葉が通じなくても、ジェスチャーと笑顔で会話が成り立つ。ケイトは確信した。この国の人々は、みんなシンセツだ。みんな、きっと味方になってくれる。MI・KA・TAなのだ。
第二章 失われた侍を求めて
翌日、ケイトは浅草を訪れた。大きな赤い提灯が掲げられた雷門の前で、彼女は立ち止まった。
「カミナリマン…」
彼女は呟いた。英語のガイドブックには「Thunder Gate」と書かれていた。ならば、ここに雷の男、カミナリマンがいるはずだ。日本のヒーローに違いない。そう信じた彼女は、通行人に尋ねてみた。
「すみません、カミナリマンは近いですか?」
中年の男性は困惑した表情で彼女を見つめた。ケイトは必死にジェスチャーを交えて説明しようとしたが、言葉が通じない。男性の表情が厳しくなり、まるで睨まれているように感じた。
「ソーリー、ソーリー…」
ケイトは謝りながら後ずさった。でも、諦めなかった。この国の人々は味方、MI・KA・TAなのだから。きっと、どこかで理解してもらえる。
仲見世通りを歩きながら、彼女は次の目標を思い出した。サムライ。侍はどこで会えるのだろう? 彼女のイメージする日本には、刀を持った侍が街を歩いているはずだった。少なくとも、どこかの公園や神社で会えるはずだ。
「サムライはどちらで会えますか?」
何人かに尋ねたが、みな首を横に振る。ある老人が英語の単語を交えて教えてくれた。
「サムライ、ノー。ヒストリー。ミュージアム」
ケイトは少し落胆したが、すぐに気を取り直した。侍が博物館にしかいないなら、大和撫子はどうだろう? 十七の顔を持つという伝説の日本女性。彼女たちには、きっと会えるはずだ。
第三章 お台場の女神とアキハバラの衝撃
三日目、ケイトはお台場を訪れた。海沿いの開放的な雰囲気、レインボーブリッジ、そして大きなガンダムの立像。すべてが近未来的で、彼女の想像していた日本とは違っていた。
海辺を散歩していると、ケイトは立ち止まった。そこに、女神像があった。自由の女神を思わせる、トーチを掲げた像。
「おダイパ女神!」
彼女は興奮して写真を撮った。フランスから送られた自由の女神のレプリカだということは、後で知ることになる。でも、その時のケイトは、日本にも女神がいることに感動していた。
その後、彼女は秋葉原に向かった。ここは別世界だった。巨大なスクリーン、点滅するネオン、アニメキャラクターの看板、耳を刺すような電子音楽。
メイドカフェの呼び込みに誘われて、彼女は階段を上った。扉を開けると、フリルのついた可愛らしい衣装を着た女性たちが一斉に振り向いた。
「お帰りなさいませ、ご主人様!」
ケイトは圧倒された。これが大和撫子なのだろうか? 彼女たちの表情は確かに変化に富んでいた。可愛らしく、時に大人っぽく、時に少女のように。十七変化という言葉が、ようやく理解できた気がした。
電気街を歩いていると、アニメのコスプレをした人々が何人も目に入った。セーラームーン、初音ミク、そして…
「あ! キューティーパニー!」
ケイトは思わず声を上げた。ピンクと白の衣装、可愛らしいポーズ。彼女が子供の頃に見たアニメ「キューティーハニー」のキャラクターだ。近づいて写真を撮らせてもらおうとすると、そのコスプレイヤーが振り返った。
男性だった。
ケイトは一瞬驚いたが、すぐに微笑んだ。そうか、この国では性別を超えて、好きなキャラクターになれるのだ。アニメでは可愛い女の子だったキューティーハニーを、男性が演じている。その自由さに、ケイトは感動すら覚えた。
その夜、ホテルの部屋でケイトはノートに走り書きした。
「この国にユメがあるのですね?」
夢。希望。可能性。この国は、彼女の想像以上に豊かだった。
第四章 理想の亀裂
しかし、一週間が過ぎる頃、ケイトは日本の別の顔を見始めた。
ホテルのテレビをつけると、ニュースが流れていた。キャスターの顔は暗く、沈んでいた。彼は何かについて深刻に語っている。字幕の漢字は読めないが、その雰囲気だけで、良いニュースではないことが分かった。政治スキャンダル、経済の停滞、少子高齢化。画面に映る数字とグラフが、何かの問題を示している。
「見ていてとっても可哀想です…」
ケイトは画面に向かって呟いた。なぜこの人はこんなに暗い顔をしているのだろう? この素晴らしい国で、何が問題なのだろう?
彼女は、オンラインで日本について調べ始めた。そして、知った。高齢化、経済の停滞、政治への不信、過労死、若者の将来への不安。輝く表面の下に、深刻な問題が潜んでいることを。
ある日、カフェで隣に座った日本人女性と会話する機会があった。英語が堪能な彼女は、ケイトの質問に率直に答えてくれた。
「政治家は嘘をつきませんか?」
ケイトは、ガイドブックに書かれていた「日本人は正直」という言葉を信じて尋ねた。
女性は苦笑いした。「残念ながら、そうとは言えないわ。政治家のスキャンダルは後を絶たない。公約を守らない人も多い」
「でも、先生は生徒を守りますよね?」
「守る先生もいる。素晴らしい教師もたくさんいる。でも、いじめを見て見ぬふりをする先生もいるし、生徒よりも体面を気にする学校もある」
「税金は無駄には使わないんですよね?」
女性は深いため息をついた。「それが一番の問題かもしれない。多くの国民が、税金の使い方に疑問を持っている。無駄な公共事業、天下り、不透明な予算配分…」
ケイトは混乱した。彼女が夢見た日本と、現実の日本。その間に、大きな隔たりがあった。
「だから…MI・KA・TA」
ケイトは呟いた。だからこそ、味方が必要なのだ。この国の人々は、問題を抱えながらも、互いに支え合おうとしている。
第五章 夜明けを探して
「どこから夜は明けて来ますか?」
ある朝、皇居の周りをジョギングする人々を見ながら、ケイトは尋ねた。誰に尋ねるでもなく、空に向かって。
もちろん、太陽は東から昇る。でも、彼女が尋ねたかったのは、希望はどこから来るのか、ということだった。暗いニュース、社会問題、停滞感。それでも、人々は朝を迎え、走り続けている。その希望は、どこから来るのだろう?
坂本龍馬の資料館を訪れた日、ケイトは龍馬の生涯を知った。幕末という混乱の時代に、新しい日本を夢見た男。身分制度に縛られず、西洋の技術を取り入れ、日本の未来を切り開こうとした男。そして、志半ばで暗殺された男。
「リョーマは泣いてやしませんか?」
ケイトは、龍馬の写真を見つめながら呟いた。もし龍馬が今の日本を見たら、どう思うだろう? 彼が命を懸けて夢見た国は、実現したのだろうか? 政治家の汚職、若者の無気力、失われた理想…龍馬は、泣くのだろうか?
しかし、資料館の老齢の館長が言った言葉が、ケイトの心に深く刻まれた。
「龍馬は、完璧な国を目指したのではありません。より良い国を目指したのです。完璧など、存在しません。大切なのは、諦めずに前に進み続けることです。龍馬の精神は、それです」
ケイトは理解し始めた。この国には誇りがある。完璧ではないけれど、より良くなろうとする誇り。問題があっても、諦めない心。それが、この国の本当の強さなのかもしれない。
第六章 笑いと涙の発見
ケイトの日本探索は、時に滑稽な誤解に満ちていた。そして、その誤解こそが、彼女に日本の深さを教えてくれた。
「ブシドウは首都高速ですか?」
彼女は本気で、武士道という哲学が、首都高速という場所で実践されていると思っていた。タクシー運転手は大笑いした後、丁寧に説明してくれた。武士道とは、侍の生き方、倫理観であり、場所ではないこと。そして、その精神は今も、形を変えて日本人の心に生きていることを。
「名誉、忠誠、自己犠牲。今の日本人全員が守っているわけじゃないけどね」と運転手は付け加えた。「でも、どこかに残ってる。サラリーマンの働き方、職人の仕事への姿勢、スポーツ選手の精神…形を変えて、武士道は生きてるんだよ」
「カブキザは歌舞伎町にはないんですか?」
新宿で迷子になったケイトは、警察官に尋ねた。警察官は優しく地図を広げ、歌舞伎座は銀座にあることを教えてくれた。歌舞伎町と歌舞伎座は、名前が似ているだけで、全く違う場所だと。
「なぜ同じ名前なのに、違う場所なんですか?」
ケイトの質問に、警察官は苦笑いした。「歌舞伎町は、昔、歌舞伎の劇場を作る計画があったんです。でも、実現しなかった。名前だけが残ったんですよ」
「ジャパニーズ、コンプリケイテッド…」とケイトは呟いた。
日本料理の奥深さも、ケイトを驚かせた。ある日、定食屋で注文した味噌汁。その具は、豆腐とワカメだった。シンプルだが、その味わいは深い。出汁の文化、旨味という概念。彼女の味覚は、新しい世界に目覚めた。
「ミソスープの具は豆腐とワカメ」
ケイトはノートにメモした。料理は文化だ。シンプルさの中に、深い哲学がある。
そして、納豆。朝食のバイキングで初めて挑戦したとき、ケイトは戸惑った。粘る。糸を引く。匂いも独特だ。
「ネバダ…ネバー…ネバネバ…」
彼女は箸で納豆を持ち上げながら、言葉遊びを楽しんだ。故郷のネバダ(Nevada)と、この不思議な食べ物。音が似ている。シャバダ、ダバダ。言葉の響きが楽しい。日本語は音楽のようだ。
味は…正直言って、まだ好きになれなかった。でも、それもまた日本の一部だ。すべてを愛する必要はない。理解しようとすることが、大切なのだ。
第七章 歌と踊りの中で
旅の二週間目、ケイトは新宿の小さなライブハウスに足を踏み入れた。ホテルのフロントスタッフが教えてくれた場所だ。「若者の音楽を聴きたいなら」と。
階段を降りると、地下の狭い空間に、若者たちがひしめいていた。煙草の煙と汗の匂いが混ざり合い、空気は熱気で揺れていた。
ステージでは、五人組のバンドが演奏していた。ギター、ベース、ドラム、キーボード、そしてボーカル。彼らの音楽は激しく、切なく、そして希望に満ちていた。
ボーカルの若い女性が、魂を込めて歌った。彼女の声は、叫びのように、祈りのように響いた。
「それでもワタシ達歌います!」
ケイトは歌詞の意味が完全には分からなかったが、その感情は理解できた。諦めない。前に進む。歌い続ける。どんなに辛くても、どんなに問題があっても。
「あなたを信じて踊ります!」
観客たちは手を上げ、体を揺らし、声を合わせた。汗と熱気に包まれた空間で、人々は一つになっていた。政治への不満、将来への不安、日々の苦しみ。それらすべてを、音楽に託していた。
ケイトも、気づけば体を動かしていた。リズムに合わせて、手を叩き、足を踏み鳴らした。涙が溢れそうになった。なぜだか分からない。でも、この瞬間、彼女はこの国の人々と繋がっている気がした。
隣にいた若い男性が、英語で話しかけてきた。
「楽しんでる?」
「イエス! とても!」
「この曲、『ニホンノミカタ』っていうんだ。日本の味方、って意味」
ケイトは目を輝かせた。「MI・KA・TA!」
「そう、味方。君も、日本の味方?」
ケイトは大きく頷いた。「Yes! MI・KA・TA! アイ・ラブ・ニホン!」
男性は笑顔で親指を立てた。「ありがとう。でも、日本は完璧じゃないよ。問題だらけだ」
「知ってる。でも、それでも」
「それでも?」
「それでも、みんな歌ってる。踊ってる。諦めてない」
男性の目が潤んだ。「そうだな。それでも、俺たちは歌うんだ」
第八章 それでもニホンが
最後の夜、ケイトは東京タワーに登った。展望台から見下ろす東京は、無数の光で輝いていた。どこまでも続く街明かり。その一つ一つに、人々の生活があり、喜びがあり、悲しみがあり、希望があった。
彼女は、この三週間で見たもの、聞いたもの、感じたものを思い返した。
回転寿司の驚き、浅草での誤解、お台場の女神、秋葉原の衝撃、男性のキューティーハニー、ニュースキャスターの暗い顔、親切な人々、伝統と現代の融合、政治への不信、それでも諦めない姿勢。
完璧な国ではなかった。彼女が想像していた理想郷でもなかった。政治家は嘘をつく。先生が生徒を守れないこともある。税金は無駄に使われることもある。
でも、だからこそ、この国は美しかった。
完璧ではないからこそ、人々は努力する。問題があるからこそ、解決しようとする。暗いニュースがあるからこそ、希望を歌う。
「それでもニホンが愛してます」
ケイトは、夜景に向かって呟いた。文法は間違っているかもしれない。「日本が」ではなく「日本を」が正しいのかもしれない。でも、この気持ちは本物だった。
彼女のスマートフォンには、無数の写真と動画が保存されていた。回転寿司、雷門、お台場の女神、メイドカフェ、キューティーハニーのコスプレ、満員電車、桜の花びら、ネオンの街、富士山、笑顔の人々、そしてライブハウスの熱狂。
ノートの最後のページに、彼女は丁寧に書いた。
「この国に誇りあるのですね? はい、あります。完璧ではない誇り。でも、諦めない誇り。それが、ニホンノミカタです」
第九章 帰路、そして再会の約束
成田空港に向かうバスの中で、ケイトは窓の外を見つめた。見慣れた景色が、今は愛おしかった。整然とした住宅、清潔な街路、規律正しく歩く人々。そのすべてに、今は物語が見えた。
チェックインカウンターで、スタッフが笑顔で話しかけてきた。
「日本は楽しかったですか?」
「はい! とても楽しかったです。また来ます」
ケイトの日本語は、三週間前より確実に上達していた。
「お待ちしております」
「質問があります」
「はい、何でしょう?」
「ニホンノミカタ…正しい日本語ですか?」
スタッフは少し考えてから、微笑んだ。「日本の味方、ですね。文法的には『日本の味方』が正しいです。でも、歌のタイトルや詩的な表現として、『ニホンノミカタ』も素敵だと思います」
「ありがとうございます。私、ニホンノミカタです」
「私たちも、あなたの味方ですよ」
その言葉に、ケイトは涙が溢れそうになった。
飛行機が離陸し、高度を上げていく。眼下に広がる日本列島。海に囲まれた小さな島国。でも、その中には、豊かな文化と、複雑な歴史と、温かい人々と、そして無数の問題を抱えながらも前に進もうとする勇気があった。
ケイトは、イヤホンをつけた。出発前に買った日本のCDを流す。あのライブハウスで聴いた「ニホンノミカタ」が流れてきた。
彼女は小さく口ずさんだ。
「それでもワタシ達歌います…」
隣の席の日本人ビジネスマンが、驚いたように彼女を見た。
「その歌、知ってるんですか?」
「はい! ライブで聴きました! とても好きです!」
男性は疲れた顔をしていたが、その瞬間、微笑んだ。「良い歌ですよね。僕も好きです。辛い時に、いつも聴くんです」
「なぜ辛いですか?」
男性は少し躊躇したが、答えた。「仕事が大変で。残業が多くて。家族とも会えなくて」
「でも、歌いますか?」
「え?」
「それでも、歌いますか? 踊りますか?」
男性は驚いた顔をして、それから大きく笑った。「そうですね。それでも、歌わなきゃいけませんね」
「はい。MI・KA・TA」
「味方?」
「はい。私、あなたのMI・KA・TA。あなたも、私のMI・KA・TA」
男性の目が潤んだ。「ありがとう。外国の方にそう言ってもらえると、なんだか…頑張れます」
終章 ネバダからの手紙
それから六ヶ月後、ケイトはネバダの自宅で日本語を勉強していた。オンラインレッスンを受け、漢字を練習し、日本のニュースを見ようと努力していた。
彼女の部屋には、日本で買った浮世絵のポスター、扇子、だるま、そして東京タワーのミニチュアが飾られていた。お台場で撮った女神像の写真も、額に入れて壁に掛けてある。
ノートパソコンの画面には、航空券の予約サイトが開かれていた。彼女は再び日本に行く計画を立てていた。今度は、もっと長く。もっと深く。京都、広島、沖縄。まだ見ぬ日本を訪れたい。
友人から電話がかかってきた。
「ケイト、まだ日本のこと考えてるの?」
「うん。今度は三ヶ月滞在する予定」
「三ヶ月? あなた、本当に変わったわね。日本に行く前は、こんなじゃなかった」
ケイトは笑った。「人生が変わったの。日本は、私が思っていたような完璧な国じゃなかった。でも、だからこそ愛せる」
「どういうこと?」
「完璧な国なんて、つまらないでしょ? 問題があるから、人々は努力する。暗いニュースがあるから、歌が生まれる。政治が腐敗しているから、若者が立ち上がる。そういう国なの」
「哲学的になったわね」
「龍馬から学んだの」
「誰それ?」
「日本のサムライよ。もう死んでるけど、彼の精神は今も生きてる。より良い国を目指し続けること。諦めないこと。それが、彼の教えなの」
窓の外には、ネバダの乾いた大地が広がっていた。砂漠の夕日が、赤く大地を染めている。でも、ケイトの心は、遠く離れた島国にあった。
彼女は日記を開き、日本語で書き始めた。まだ拙い文字だが、心を込めて。
「親愛なる日本へ、
私はすぐに戻ります。あなたが完璧ではないことを知っています。でも、誰が完璧ですか? あなたには問題があります。でも、美しさも、優しさも、希望もあります。
政治家は嘘をつくかもしれない。 先生が生徒を守れないこともあるかもしれない。 税金が無駄に使われることもあるかもしれない。
でも、それでもあなたの人々は歌い続ける。 踊り続ける。 希望を持ち続ける。
だから、MI・KA・TA。 私は、あなたの味方です。
あなたを信じて、踊ります。 それでもニホンが、愛してます。
ケイトより」
彼女は日記を閉じ、窓の外の夕日を見つめた。太陽は西に沈む。でも、地球の反対側では、同じ太陽が東から昇る。
夜明けは、必ず来る。
どこから夜は明けて来るか? 東から。でも、本当の夜明けは、諦めない心から来る。龍馬が泣いているかどうかは分からない。でも、彼の精神を受け継ぐ人々がいる限り、日本の夜明けは続く。
ケイトのスマートフォンに、日本からメッセージが届いた。ライブハウスで出会った若者からだ。
「元気? また日本に来る? 今度は僕が案内するよ。君が知らない日本を見せたい。良い日本も、悪い日本も。全部ひっくるめて、これが俺たちの国だから」
ケイトは微笑んで、返信を打った。
「はい! 行きます! 私、ニホンノミカタです。Forever」
そして、彼女は立ち上がり、部屋の中で小さく踊り始た。音楽もかけずに、ただ体を揺らす。
「それでもワタシ達歌います…」
小さく口ずさみながら、ケイトは踊った。ネバダの小さなアパートの一室で、誰も見ていない中で。でも、彼女は一人ではなかった。心の中に、日本の人々がいた。ライブハウスで出会った若者たち、親切にしてくれた人々、疲れた顔で働くサラリーマン、暗い顔でニュースを読むキャスター、そして坂本龍馬。
「あなたを信じて踊ります…」
エピローグ 二度目の春
翌年の春、ケイトは再び成田空港に降り立った。今回は三ヶ月の滞在予定。ワーキングホリデービザを取得し、日本で働きながら生活する計画だった。
空港の到着ロビーで、ライブハウスで知り合った若者、タクヤが待っていた。
「ケイト! お帰り!」
「ただいま!」
ケイトの日本語は、半年前よりずっと流暢になっていた。
「日本語、上手くなったね」
「毎日勉強しました。でも、まだまだです」
タクヤは笑った。「十分だよ。じゃあ、行こうか。今日は特別な場所に連れて行くから」
車で向かったのは、東京郊外の小さな町だった。古い商店街、昔ながらの銭湯、寂れた公園。観光ガイドには載っていない、普通の日本。
「ここが俺の地元。かっこよくないだろ?」
タクヤは照れくさそうに言った。
「いいえ、素敵です」
「嘘つけよ」
「本当です。これも日本。ネオンも、お寿司が回るのも日本。でも、これも日本」
商店街を歩いていると、八百屋のおばさんが声をかけてきた。
「タクヤ! 久しぶりじゃない。その子は?」
「友達です。アメリカから来ました」
おばさんは目を丸くした。「まあ! ようこそ! 日本は初めて?」
「二回目です。日本、大好きです」
「あら、日本語上手ね! みかん、食べる?」
おばさんは、無料でみかんを二つくれた。温かさが、ケイトの心に沁みた。
タクヤの実家は、小さな二階建ての家だった。彼の母親が、手料理で迎えてくれた。味噌汁、焼き魚、煮物、漬物。回転寿司やメイドカフェとは違う、本当の日本の味。
「美味しいです」
ケイトは心から言った。
「そう言ってもらえると嬉しいわ。でも、こんな質素な料理で申し訳ないわね」
「いいえ。これが、本当の日本だと思います」
食後、タクヤの父親が話しかけてきた。疲れた顔をした、五十代の男性だった。
「日本は、どうですか?」
「素晴らしいです」
父親は苦笑いした。「素晴らしい…か。俺たちには、もうそう見えないな。毎日働いて、税金取られて、老後の不安ばかりで」
「でも、諦めていませんか?」
「え?」
「毎日、働いていますよね? 家族を守っていますよね? それが、諦めていない証拠です」
父親は黙り込んだ。そして、目を潤ませた。
「外国の人に、そう言ってもらえるとは思わなかった」
その夜、タクヤと二人で近所の公園を歩いた。桜が満開だった。夜桜。街灯に照らされた桜は、幻想的に美しかった。
「ケイト、なんで日本が好きなの? 本当に」
タクヤは真剣な顔で尋ねた。
ケイトは少し考えてから答えた。
「完璧じゃないから」
「は?」
「完璧な国だったら、好きにならなかったと思う。問題があって、矛盾があって、悩んでいる。でも、諦めない。それが美しい」
「俺たち、そんなに美しく見える?」
「うん。タクヤも、お父さんも、ライブハウスの人たちも、疲れた顔のサラリーマンも、暗い顔のニュースキャスターも。みんな、それでも歌ってる。踊ってる。生きてる」
タクヤは空を見上げた。
「龍馬は、泣いてるかな」
「分からない。でも、泣いてても、諦めてはいないと思う」
「そうだな」
風が吹いて、桜の花びらが舞った。ピンクの雪のように、二人の周りを舞い落ちる。
「ケイト」
「なに?」
「ありがとう。MI・KA・TAでいてくれて」
「こちらこそ。私のMI・KA・TAでいてくれて」
二人は笑い合った。
最終章 轍の先に
三ヶ月の滞在中、ケイトは東京の小さなカフェで働いた。英会話の先生としても、週に二回教えた。そして、日本をもっと深く知った。
満員電車の辛さ。長時間労働の厳しさ。閉塞感。同調圧力。外国人への微妙な差別。完璧ではない、この国の現実。
でも、同時に知った。困っている人を助ける優しさ。細部へのこだわり。四季の美しさ。伝統を守る誇り。そして、問題を認識しながらも、より良くしようと努力する人々の姿。
ある日、カフェに一人の老人が来た。杖をついた、九十歳近い男性。彼は毎日、同じ時間に来て、ブレンドコーヒーを注文した。
ケイトが英語で話しかけると、老人は驚いた顔をした。
「アメリカの方ですか?」
「はい。ネバダから来ました」
「ネバダ…遠いところから。なぜ日本に?」
「日本が好きだからです」
老人は優しく笑った。
「私は、戦争を経験しました。この国が焼け野原になったのを見ました。そして、復興するのも見ました」
「大変でしたね」
「ええ。でも、希望がありました。みんな、より良い国を作ろうと必死でした。今は…」
老人は言葉を切った。
「今は、どうですか?」とケイトは優しく尋ねた。
「今は、希望を見失っている人が多い気がします。でも」
「でも?」
「あなたのような若い人が、外国から来て、日本を好きだと言ってくれる。それが、私たちの希望です」
ケイトの目から涙が溢れた。
「私が希望をもらっています。この国から」
老人は静かに頷いた。
「希望は、与え合うものなのかもしれませんね」
帰国の前日、タクヤたちがサプライズパーティーを開いてくれた。ライブハウスで出会った仲間たち、カフェの同僚、英会話の生徒たち。みんなが集まってくれた。
そして、バンドが演奏した。あの曲を。
「ニホンノミカタ」
みんなで歌った。ケイトも、拙い日本語で一緒に歌った。
「それでもワタシ達歌います」
「あなたを信じて踊ります」
「それでもニホンが愛してます」
涙と笑顔の中で、ケイトは理解した。
これが、希望の轍なのだ。
一人では残せない。でも、みんなで歩めば、轍は残る。完璧な道ではない。曲がりくねって、時に後退もする。でも、確実に前に進んでいる。
龍馬が夢見た国は、完成していない。おそらく、永遠に完成しない。でも、その未完成さこそが、希望なのだ。より良くなれる余地があるということ。
終わり、そして始まり
飛行機が日本を離れる直前、ケイトはスマートフォンに最後のメッセージを打った。
「ありがとう、日本。あなたは完璧じゃない。でも、だからこそ美しい。
政治家は嘘をつくかもしれない。 先生が生徒を守れないこともあるかもしれない。 税金が無駄に使われることもあるかもしれない。 ニュースキャスターの顔は暗いかもしれない。
でも、
それでもあなたの人々は歌う。 踊る。 希望を持ち続ける。
どこから夜は明けて来るのか? 東から。 でも、本当の夜明けは、諦めない心から来る。
龍馬は泣いているかもしれない。 でも、諦めてはいない。 彼の精神は、今も生きている。
ブシドウは首都高速じゃない。 カブキザは歌舞伎町にはない。 ミソスープの具は豆腐とワカメ。 納豆はネバダみたいにネバネバ。
笑えることも、間違えることも、全部が学び。
MI・KA・TA。 私は、あなたの味方。 あなたも、私の味方。
この国に誇りはあるか? はい、あります。 完璧ではない誇り。 でも、諦めない誇り。
この国に夢はあるか? はい、あります。 簡単には叶わない夢。 でも、追い続ける夢。
それでもワタシ達は歌います。 あなたを信じて踊ります。 それでもニホンが、愛しています。
また会おう、日本。 必ず戻ってくる。
この轍の先で。
ケイト・マクラーレン ネバダより、愛を込めて」
メッセージを送信し、ケイトは窓の外を見た。眼下には、青い海が広がっている。その向こうに、日本がある。
彼女は微笑んだ。
希望の轍は、海を越えて続いている。
ネバダと日本を繋ぐ轍。 過去と未来を繋ぐ轍。 問題と希望を繋ぐ轍。
そして、一人一人の心に刻まれた轍。
完璧ではない。 でも、確かに存在する。
それが、ニホンノミカタ。
ニホンノミカタ-ネバダカラキマシタ-(2008)/矢島美容室
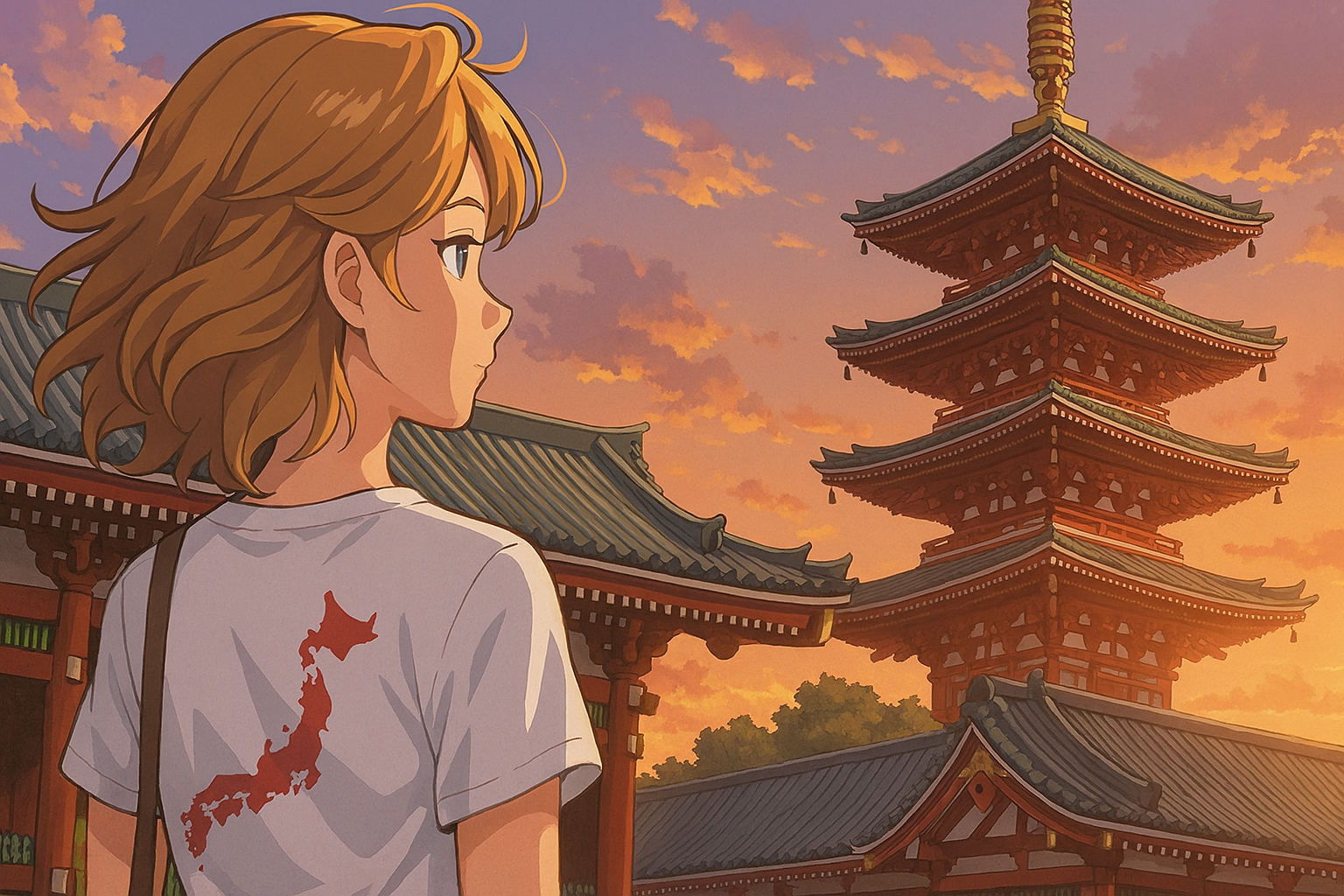


コメント